
お役立ちコラム
退職者が続出する理由とは?そのとき企業が取るべき対策8選
終身雇用が崩壊しつつある今、かつてよりも退職をライトに考える社会人は多くなってきていると言われています。その背景としては日本経済の衰退や、社会の傾向として個性や自分の気持ちを大事にする動きが強くなってきたことも挙げられるでしょう。さらに今はSNSをはじめとする媒体から膨大な量の情報をキャッチすることが可能になっているため、他社の好条件の情報や、転職の成功エピソードに触れる機会も多く、「転職をしたい」という気持ちが強まる機会は非常に多いと言えます。 また、退職は連鎖してしまうことがあるため、同じ会社の社員や友人が転職する姿を見ることによって、「自分も思い切って転職してみようかな」という思いが伝播してしまわないように会社側は十分に注意を払う必要があります。 そこで今回は、退職者が続出してしまう理由と、そのときに企業が取るべき対応についてご紹介します。
退職が個人の問題であれば連鎖せずに単発で終わる可能性が高いですが、連鎖的に退職が続いているのであれば、企業の環境や採用の仕組みなどが大きな原因となっているケースを考えるべきでしょう。
企業が採用活動を行う際には、欲しい人物像が必ずあります。この人物像を正しく理解していないと、採用担当者の独断で採用をしてしまったり、ミスマッチになってしまったりする可能性があります。
「欲しい人物像」は必ずしもすべての部署で共通するものではありません。また、そのタイミングによっても、欲しい人物像が異なる場合があります。つまり採用担当者は、会社として望ましい人物像を理解しつつ、新たに社員を増やしたい部署が求めている人物像も理解した上で採用活動に携わらなければいけません。そのためには、各部署や経営層と連携を図り、「欲しい人物像」をより具体的にして置く必要があるのです。
これがうまくできていないと、ちょっとしたことで転職や退職が頭に浮かぶ社員が多くなるでしょう。
採用担当者は、採用コンセプトや職場の雰囲気、業務内容などを十分に理解した上で、採用希望者がそれに該当する人物かどうかを見極める力が求められます。
そのため、採用コンセプトなどを正しく理解しているのに退職者が相次ぐ場合は、採用担当者が採用希望者の本質を見抜けていなかった可能性があります。
もしくは、採用コンセプトは理解しているものの、職場の雰囲気や業務内容を理解しておらず、勝手に「大丈夫だろう」という思い込みで進めてしまった結果、退職に繋がってしまったということもありえるでしょう。
採用希望者の持っている情報に誤りがあると、入社後にイメージの違いや違和感から退職を考える可能性があります。採用希望者の持つ情報というのは、採用希望者が自ら収集した情報ももちろんありますが、採用担当者が偽ったり誤ったりして伝えた情報や、伝え方によって誤った情報を認識させてしまった情報も含まれます。
嘘偽りがない正しい情報を伝えることは大前提ですが、伝え方やコーポレートサイトでの情報の出し方にも注意しましょう。
入社する社員は、「この条件、この環境であれば働きたい」と思い入社をしてきます。例外として、「この会社で学費を稼いで、学びなおすつもりだった」「夫の転勤で引っ越しが必要になった」「家庭環境が変わった」などのケースはこの限りではありませんが、会社は条件や環境について偽りない情報を伝えていて、その上で入社を決めたのであれば、社員の気持ちが大きく変わらない限りはそうそう退職という決断には至らないものです。
採用過程に問題はなくとも、職場の環境や労働条件に問題があり、せっかく入社した社員をいわゆる"つぶす"ようなことをしてしまった…ということは、残念ながら往々にして起こり得ることです。
これについては原因が様々で、たった1人の既存社員が元凶であることもあれば、業務量の問題であったり、多くの社員が元凶になっていたりすることもあり、非常に複雑である可能性が高いです。内情をよく知りつつ、客観的な視点を持てる人物がいない限りは原因の分析も難しく、解決することは困難を極めます。
最も重要なことは退職者へのヒアリングです。退職の続出を防ぐためには、その理由を知らないことには防ぎようがありません。そこで一番重要となってくるのが、退職者へのヒアリングです。その際、元凶となってしまった社員などからヒアリングをかけてしまうと本当の意見を聞く事ができないため、匿名性の高い手段でヒアリングを掛けたり、関係のない部署の社員からヒアリングを掛けたりするなどして、できるだけ忌憚のない意見を聞くことができるように工夫しましょう。
逆に、最もよくないことはヒアリングを行わずに「退職は個人の問題であり、会社には原因が無い」と決めつけて何も対策を取らないことです。この方針を取った場合、退職を止めることは難しいでしょう。
退職者へのヒアリングを行ったあとは、客観的視点で当事者や関係部署に事実確認を行いましょう。退職者の話はとても重要な情報ですが、それを100%鵜呑みにすることはよくありません。また先入観を防止するために第三者的視点が必要になりますので、時には別の部署の社員や、外部の人間に協力を仰ぎましょう。
原因がおおむね想定できたあとは、経営陣、当該部署、採用担当部署でミーティングを行い、原因に応じた対策を考えましょう。原因が1つということはまずなく、複数の原因があるかと思いますが、原因と思しき要素すべてに対して手あたり次第にアプローチするよりも、重要度を決めて計画的かつ丁寧にアプローチしていきましょう。
こういった問題はとても根強く、組織崩壊でもしない限り一気に解決するということは難しいため、長い道のりで計画的に取り組む覚悟を持ちましょう。
求めている人物像を採用担当者が正しく理解するためには、各所とコミュニケーションを取っておくことがベストです。メールやチャットなどで求める人物像をヒアリングすることも可能ではありますが、実際に配属される部署に赴いてみたり、現場の生の声をヒアリングしたりすることで、言語化されなかった情報を手に入れることができる可能性もありますので、より精度を上げるためには一度生のコミュニケーションを取ってみても良いでしょう。
採用担当者には、人の中身を見極める力が求められます。これまで自分の人生経験を基に何となくの基準で人材を見てきた採用担当者は、一度初心に帰って採用に関する記事などを読んだり、初対面の人がたくさん集まってコミュニケーションを取る場などに出向いたりして、自分の目を鍛えてみても良いかもしれません。
採用担当者には耳が痛い内容ではありますが、「自分は大丈夫」と思い込んだままだと状況は改善しません。
採用活動時はついつい自社の良いところばかりを伝えたくなってしまいますが、その結果としてミスマッチを生んでしまっては、時間的なコストも金銭的なコストも無駄になってしまいます。
とりあえずの頭数が必要なのであれば派遣会社を利用するなどの手段もありますので、正社員を採用したい場合は長期にわたって定着させることを前提として、リアルな業務内容や雰囲気を伝えましょう。
社員はボランティアや趣味で来ているわけではなく、基本的には仕事をして生計を立て、生きていくために会社に来ています。つまりそのバランスが取れていないことが常になってしまった場合、ふとした時に「退職」の二文字が頭に浮かぶことは至極当然のことです。
業務量が膨大になっている場合は、ワークライフバランスの見直しを行いましょう。職場の人間関係やハラスメントが問題になっている場合は、相談窓口の設置や教育プログラムの実施を検討しましょう。給与は業界・地域・国内の水準と比較して競争力のある給与体系にしましょう。評価制度は明確にしましょう。
これらの基本的な職場環境が整備されていてこそ、やりがいや成長意欲を追い求めることができるようになります。
ただ、これらを充実させると会社としては「こんなに環境がいいのだから退職するのは仕方がない」と思いたくなりますが、それは禁物です。また別に理由が潜んでいるという可能性を忘れず、他の原因を探りましょう。
入社後すぐに定着できるよう、オンボーディングの強化として充実した研修やサポート体制を構築しましょう。入社後に充実したサポートが無いと、社員は右も左もわからない状態で放置されることになり、「この会社で大丈夫だろうか」といった不安な気持ちを抱かせることになりかねません。その不安が、のちに退職に繋がることも十分にあり得ます。
新入社員を採用するときにはそのようなことが絶対に無いように、先に研修や教育スケジュールを構築した上で迎え入れるようにしましょう。
マネジメント能力が低い管理職をそのまま放置してしまうと、マネジメントがうまくいかずに一人ひとりの仕事の負担が個人任せになったり、モチベーションがあがらなかったり、帰属意識が低下したりと良いことがありません。
管理職に向けて定期的に研修を行ったり、360°評価を行ったりして、マネジメント能力の向上や部下のサポート能力が備わっているかを定期的にチェックし、見直しを行うようにしましょう。
費用は発生してしまいますが、人材マネジメントに強い外部専門家の助言を受けることも解決手段の一つです。客観的な視点と専門家ならではの知見を活かし、効率的に解決策を見出すことができるでしょう。
帰属意識を高めるために社内イベントを行うことも有効です。 社内イベントといっても種類はいくつもあり、イベントによって効果も異なるため、自社の悩みにあったイベントを選択して実施しましょう。
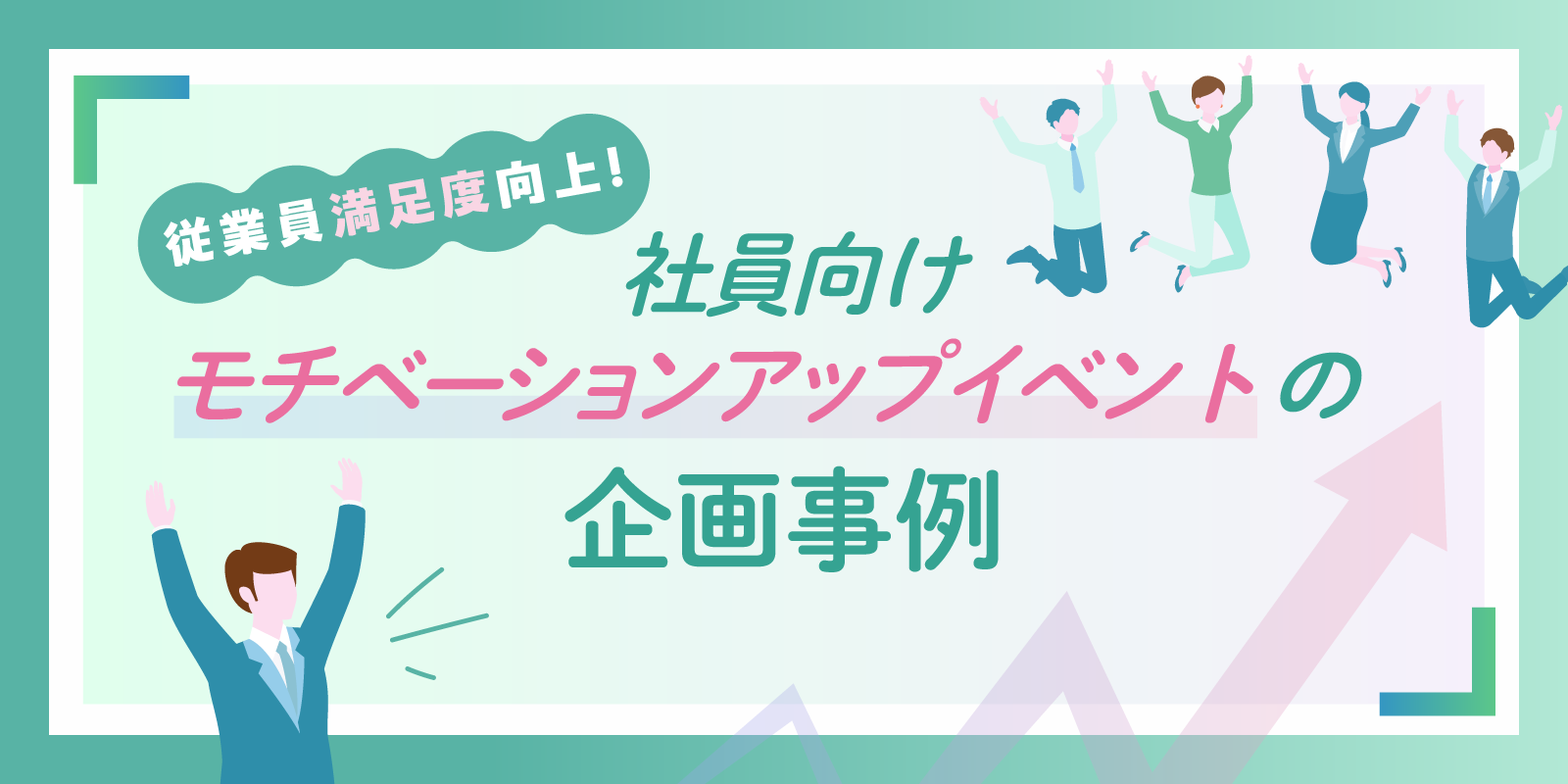
【従業員満足度向上!】社員向けモチベーションアップイベントの企画事例
従業員満足度向上とモチベーションアップに効果的なイベント企画のポイントと、具体的な企画事例を詳しく紹介していきます。
詳しくはこちら
しかし、前提として最低限の労働環境などが整備されていないと、社員は心からイベントを楽しむことができませんので、ベースが整った上で実施するようにしましょう。
この記事では、退職者が続出する原因とそれに対して企業が取ることのできる対策をご紹介しました。最後には対策の一つとしてイベントの実施も挙げさせていただきました。
エス・ブイ・シーグループはイベントの企画、制作から当日の運営までをワンストップで行います。周年イベントももちろんお任せください!その際には、今回記事で紹介した内容以外にも、ご状況に合わせて様々な企画のご提案をさせていただきます。 ほかにも、社員総会や表彰式といった社内イベント、記念式典、合同企業説明会、eスポーツイベントなど、オンライン・オフラインを問わずどんなイベントでもお任せください。開催方法や内容が決まっていなくても、丸投げOKです!お客様の目的に合わせたイベントをご提案しますので、お気軽にご相談ください。エス・ブイ・シーグループはイベントを通じて感動を創造していきます!
DATE
2025年03月17日
CATEGORY
お役立ちコラム
タグ
- #ニュースリリース (39)
- #社内イベント (34)
- #社内表彰式 (13)
- #ベガルタ仙台 (11)
- #社員総会 (9)
- #周年イベント (9)
- #イベント出展 (8)
- #コンテンツ (8)
- #展示会 (8)
- #懇親会 (6)
- #合同企業説明会 (6)
- #内定式 (6)
- #プレゼン大会 (5)
- #入社式 (4)
- #BPO (4)
- #採用情報 (3)
- #イベント外注 (3)
- #歓迎会 (3)
- #成功事例 (2)
- #内定者 (2)
- #研修 (2)
- #大学 (2)
- #重要なお知らせ (1)
- #事務局 (1)
- #オンライン説明会 (1)
- #インターンシップ (1)
- #就職活動 (1)

